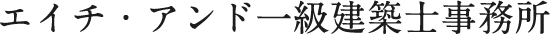岐阜県立森林文化アカデミー
2025.03.27
自宅とアトリエ裏山の整備に際して里山のことを学びたく、植物生態学がご専門の柳沢先生と林業がご専門の大洞先生をご紹介頂けることとなり、岐阜県立森林文化アカデミーへ行って来ました。


お二人には裏山の状況や考えていることをご説明し、柳沢先生からはスケッチを交えて様々なアドバイスを頂きました。


短い時間の中でも本当に沢山のことをお話し頂いたのですが、ここでは書ききれないので改めてご紹介させて頂きたいと思います。
また柳沢先生には講師として篠山にお越し頂けることとなりましたので、またH&での勉強会のご案内をさせて頂ければと思います。
主な校舎は北川原温さんによるもので、岐阜県産材を用いた素晴らしい建築でしたが、このアカデミーの凄いところは比較的に長い歴史があり、広い構内があり、沢山の先生がいらっしゃり、沢山の建築があり、沢山「沢山」があるのですが、その全てが環境や美しさ、人の暮らし、教育といった色々な文脈においても破綻なく、というか高いレベルで調和していることがこのアカデミーの最大の特徴なのではないかと思います。
林業、森林環境教育、木造建築、木工という四つの分野に分かれているのですが、一通りの校舎はもちろんのこと製材所あり、人工乾燥機あり、充実した木工室あり、構造試験室あり、ゲスト宿泊施設あり、原木を並べる土場あり、地域の子供たちが集える遊び場あり、高性能林業機械あり、などなど。


北川原さんが設計したもの以外は都度建築家でもある教員が設計し、実験や教育も兼ねながらひとつずつ建築して来ています。


そして毎年一棟ずつ、その年の生徒が設計から施工までを自力で建設する「自力建設の教育プログラム」により必要な建物が新築・増築されて行きます。
外部の動線上に必要な庇や渡り廊下であったり、大工道具を収納する小屋であったり、自然エネルギーを使った木材乾燥小屋であったり、休憩小屋であったり、シャワー室であったり、屋外階段であったり。




全二年のプログラムの内一年目は設計、二年目は施工という流れで行政の認可もきちんと提出した上で進められています。
生徒の為のプロジェクトではありますが、先生たちも教えながら実験を通して勉強になっている、とのことでした。


そうした機械や施設は生徒であればだれでも使いたいだけ使えるとのことで、こんな夢のような環境が日本にあったのか、ととても嬉しくなりました。




岐阜県立のこの施設。公共というのは本当に世の中に必要なことをやろうとすると様々な横やりが入り中々上手くいかず、大きな流れになりにくいものという印象が強くあります。
そんな中でこれだけのことが高いレベルで同じ日本で実現されているということは、自分たちの未来にとってもとても勇気が出る有意義な一日でした。
ご案内頂きました辻先生、柳沢先生、大洞先生、そしてご対応して下さった教員の皆様ありがとうございました。